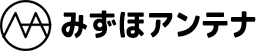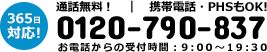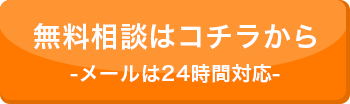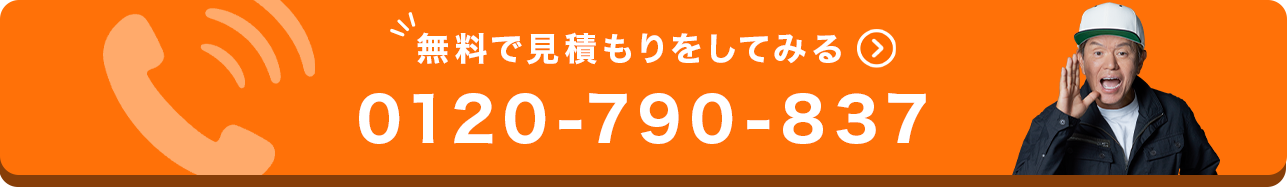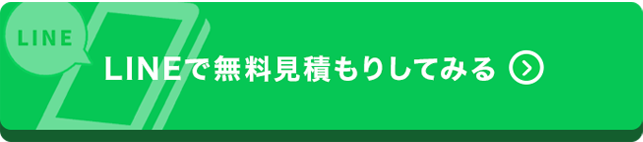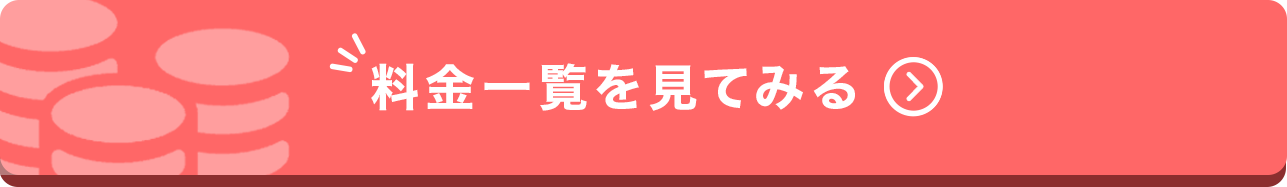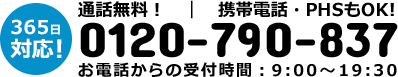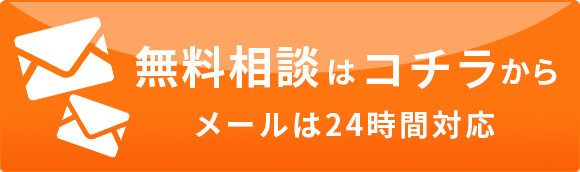慌ただしい引っ越し作業が一段落し、テレビの電源を入れてもテレビがつかないとなると焦りますよね。
こちらでは、引っ越しでテレビを梱包する際の手順や注意点、転居先でテレビが映らない原因や対処法について詳しくご紹介します。
また、一見むずかしそうな配線やチャンネル設定もご説明しています。
手順さえわかっていれば、家電が苦手な方も簡単に対処できます。
引っ越し後にテレビがつかないとアタフタすることが無いよう事前に準備しておきましょう。
引っ越し後にテレビが映らない原因と対処法
引っ越し後にテレビが映らない時、以下6つの原因が考えられます。
こちらでは、上記6つの原因を深掘りし、原因に合わせて対処法もあわせてご紹介していきます。
是非参考になさってください。
原因①テレビの不具合や故障

運搬時の衝撃によりテレビが故障した可能性があります。
テレビの寿命は一般的に6~10年程と言われており、運搬による振動で不具合が生じたと考える事もできます。
10年以上使っているテレビの場合には、買い替えを検討されても良いでしょう。
近年の高機能なテレビの場合、バグや誤作動により一時的に映らない状況となっている場合もあります。
まずは落ち着いてテレビの再起動を行いましょう。
再起動の仕方はメーカーの取扱説明書に記載されています。
ー関連記事ー
☞【テレビ故障の対処を症状別にご紹介!買い換えた方が安いの?】
原因②アンテナケーブルの故障や不具合

テレビケーブルの端子の中にある針金は細く、配線する中で針金が曲がったり折れたりすることがあります。
針金が折れたり曲がったりすることにより、接続できなくなります。
テレビケーブルは、多くの方がテレビ購入時に一緒に揃えられます。
したがって、テレビケーブルも長年使い続けているため劣化している可能性も考えられます。
テレビケーブルはどのテレビでも利用できるので、転居をきっかけに新品に購入しても良いでしょう。
一般的に数百円から数千円程度で購入できます。
ー関連記事ー
☞【テレビのアンテナケーブルの選び方・配線方法・おすすめ商品を紹介!】
原因③配線不備

配線の不備はよくあるミスの1つです。
地デジにさすべき配線を「BS・CS」に間違えて接続していることが多々あります。
また、挿入口があっていてもケーブルがきちんとささっていない場合もあります。
配線不備はすぐに直すことができます。
まずは配線にミスが生じていないか確認しましょう。
先述しましたが、引っ越し前の梱包の際にどの配線がどの差込口に接続するか、それぞれに目印をつけておくとミスを未然に防げます。
ー関連記事ー
☞【テレビアンテナケーブルのつなぎ方をお部屋の端子別に解説】
原因④アンテナの不具合や故障

アンテナの不具合によってテレビが映りにくい、映らない場合があります。
アンテナ不具合には以下のような原因が考えられます。
・アンテナの向きが合っていない
・アンテナ本体の劣化や故障
・障害物によりアンテナレベルが低い
・電波が強すぎる(アッテネーターをいれるなどの対処が必要)
・山間部で電波がきちんと届いていない
これらの不具合は素人で判断することは困難です。
テレビ本体や接続方法、設定に問題がない場合には専門業者に相談してみましょう。
ー関連記事ー
☞【テレビアンテナ修理の費用相場はいくら?故障原因や業者の選び方を解説】
原因⑤電波の弱い地域であった
電波はお住まいの地域によって電波レベルが異なります。
電波塔から近い地域は電波が強く、電波塔から離れれば離れるほど電波は弱くなります。
また、電波塔とご自宅の間に鉄筋コンクリート製の高層ビルなど障害物がある場合や山間部などは、電波塔からの距離にかかわらず電波が弱くなる場合があります。
強い地域でしか使えない「室内アンテナ」を旧居で使っていて、電波の弱い地域で同様のアンテナを使おうとした際、利用できないということは良くあります。
アンテナを引き続き利用されたい方は、専門業者に依頼し転居先の電波状況を前もって調べておくことが重要です。
ー関連記事ー
☞【アンテナレベル(受信レベル)が低いテレビの映りが悪い?原因や対処法などを解説!】
原因⑥アンテナがない
新築の一戸建て住宅にお引っ越しされる場合、アンテナ設置はご自分で手配する必要があります。
お引っ越しとなるとやることは山積みです。
アンテナの設置まで気がまわらず、後回しにし忘れてしまったというケースは少なくありません。
また、BS放送を視聴するためにはBSアンテナが必要になります。
アンテナの新設は専門業者に事前に依頼しなければいけません。
引っ越しシーズンなどは混み合うケースが多く、希望日程を抑えにくくなります。
前もってのご相談をおすすめします。
ー関連記事ー
☞【中古の戸建て物件に引っ越したらテレビのアンテナがない?対処法について解説!】
☞【新築のアンテナ工事のタイミングは?いつ始めればいい?最適な時期・依頼先・費用相場を紹介】
原因⑦B-CASカードが抜けていた

地デジ放送もBS・CS放送も、基本的にはこちらのB-CASカードを差し込まないと、番組を視聴することはできません。
引っ越しの時にテレビを梱包する際、上記写真のようなカードを抜いたりした覚えはありませんか。
B-CASカードはいろいろな色をしており、サイズも異なります。
テレビを新しく購入すると付属で付いてくるものなので、引っ越しの際にテレビを新しく買い替えたという方も要注意です。
テレビの背面もしくは側面に、カードを挿入する箇所があるので、きちんと差し込まれているか確認してみましょう。
ささっているように見えても、引っ越しでテレビを動かしたときにきちんと接続されない状態になっている可能性も考えられます。
挿し直してみるのが安心です。
ー関連記事ー
☞【B-CASカードのエラーの原因とすぐできる対処法を解説!カードの購入方法も】
引っ越し後のテレビの配線方法

地デジ放送を見るための配線手順
①壁にあるテレビ端子に、テレビケーブルをつなぐ
②テレビを設置し、テレビ本体の裏にある「UFH/地デジ」と書かれた場所にテレビケーブルを差し込む
③テレビにB-CAS(ビーキャス)カードを差し込む
④テレビの電源を入れ、チャンネル設定を行う
チャンネル設定はテレビのメーカーによって、設定方法が異なります。
対象メーカーの取扱説明書を確認しましょう。
新築では基本的にテレビ端子が備え付けられていますが、テレビ端子がない場合には端子の増設工事が必要です。
地デジ放送と衛星放送を見るための配線手順
①壁のテレビ端子にテレビケーブルと分波器をつなぐ
※分波器とは、地デジと衛星放送の電波を分ける際に使う専用機器のことです。
②テレビを設置し、テレビ本体の裏にある「UFH/地デジ」「BS・CS」を書かれた場所に分波器から伸びているコードを差し込みます。
③テレビにB-CAS(ビーキャス)カードを差し込む
④テレビの電源を入れ、チャンネル設定を行う
衛星(BS・SC)放送を視聴するためには、BS・SC専用のアンテナを設置する必要があります。
レコーダーの配線手順

| ①レコーダーを中間に挟むようにアンテナケーブルを接続 |
| レコーダーの裏には、地デジ用とBS/CS用の出力端子が2つ、アンテナの入力端子が2つありますので、それぞれをアンテナケーブルで接続します。 |
| ②テレビとレコーダーをHDMIケーブルで接続 |
| 映像と音声の信号を送るためには、テレビとレコーダーをHDMIケーブルで接続する必要があります。 テレビのHDMI入力端子とレコーダーのHDMI出力端子をHDMIケーブルで接続するだけです。 テレビ側の端子には複数種類がありますので、接続する番号をきしんと確認しながら進めていきましょう。 |
| ③レコーダーの電源コードを接続 |
| 壁のコンセントとレコーダー端子を付属の電源コードで接続し完了です。 |
テレビのチャンネル設定の手順

引っ越しをして地域が変わる場合には、再度チャンネル設定をし直しましょう。
地域によって、テレビは受信できる放送局が異なります。
他県にお引越しされた場合、チャンネルの再設定をしなければ地上デジタル放送が受信できないことがあります。
引っ越しにより放送している番組が変わり戸惑う方もいらっしゃいますが、受信できる番組が地域によって異なることが原因です。
そのため、テレビ操作で受信できる放送局を探し登録と、リモコンですぐに視聴できるようチャンネル設定が必要です。
お引越しに限らず、テレビを買い替えたときもチャンネル設定は必要になります。
チャンネル設定は、まずは地上デジタル放送から行います。
設定の大まかな流れですが、メーカーによって少しずつ操作が異なります。
こちらでは、代表的なメーカー(製品)のチャンネル設定方法をご紹介しますので参考になさってください。
尚、各メーカーの取り扱い説明書や公式サイトでもチャンネル設定方法は紹介されています。
実際に設定を行い際には、そちらをご確認の上ご対応下さい。
ソニー:BRAVIA

東芝:レグザ
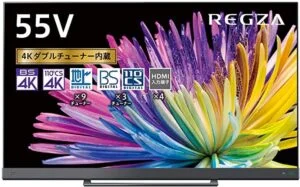
※参考
シャープ:AQUOS

※参考
パナソニック:VIERA
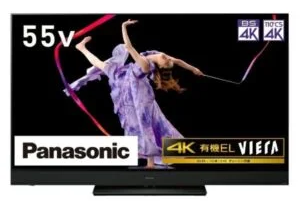
※参考
フナイ:ハイビジョン有機ELテレビ

※参考
日立

日立のテレビは、ウー(Wooo®)が有名です。
尚、衛星放送やCS有料放送を視聴される場合には、設定は基本的に地上デジタル放送の設定と同じですが、別途設定が必要になります。
ハイセンス

尚、衛星放送やCS有料放送を視聴される場合には、アンテナの受信状態を確認する流れになります。
地上デジタルチャンネルの設定後に合わせて確認するようにしましょう。
BS・CSチャンネルの設定手順
こちらでは、BS・CSチャンネルの設定手順について詳しくご紹介します。
メーカーにもよりますが、基本的には地上デジタル放送の設定と変わりません。
BS・CSはチャンネル数が多ため、お好み合わせて視聴したいチャンネルと登録しておきましょう。
BS・CSはチャンネルの場合チャンネル数が多く、ご自分でチャンネル登録をしていないと毎回視聴する時に視聴するチャンネルを探さなければいけません。
従って、前もってチャンネル登録を行うことをおすすめします。
どうしてもテレビが映らない場合の依頼先
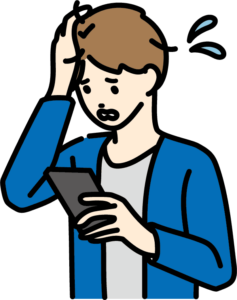
テレビが映らない時の原因や対処法についてご紹介しましたが、一通りの対処を施しても一向にテレビが映らない時は専門業者に相談しましょう。
家電量販店や町の電気屋さん
ビックカメラやヤマダ電機など大手の家電量販店では、家電の販売に限らずチャンネル設定やアンテナ設置などもお願いできます。
ご自宅に出向くスタッフは、基本的に家電量販店が依頼した下請け業者になります。
また、個人経営の街の電気屋さんなども対応していますが、価格や対応などお店によって異なります。
テレビを購入する前なら、購入から設置までまとめて頼める点は魅力的です。
しかし、下請けや外注業者の場合、情報の共有がなく工事まで時間がかかってしまうこともあります。
また何か不具合が発生した際、下請けですと駆け付けまでに時間がかかってしまったり、個人経営の場合にはその業者が閉業してしまったりする場合もあります。
他の業者を呼ぶ必要があるケースもありますので、依頼先は慎重に決めましょう。
引越し業者
引っ越し屋さんには一般的に「オプションサービス」があり、テレビの取り外しや運搬、設置などをお願いできます。
引っ越し代金に加え、オプション料金が上乗せになるので少々割高になることも考えられます。
価格は引っ越しの規模やオプション内容によりことなりますので、事前に訪問を依頼し見積もりを取るようにしましょう。
オプションサービスは引っ越し前日までに依頼する必要があります。
引っ越し後や当日に付け加えることはできませんので注意が必要です。
テレビのセッティングや設定までお願いしたいという方は、訪問見積もりの際に前もって聞いてみましょう。
尚、テレビの故障原因が引っ越しによるものと明らかな場合は、まずは引越し業者に連絡しましょう。
例えば、引越し業者による梱包や搬送が不十分で、目の前でテレビを落とされ、液晶画面が破損した場合などです。
この場合は、修理費用や損害賠償を請求できることもあります。
それ以外は、なかなか引越し業者によるものと明らかにすることが難しく、保証を受けることが難しいでしょう。
詳しい保証内容については、契約書なども確認し早めに問い合わせることが大切です。
アンテナ業者
アンテナ業者はテレビアンテナ設置に限らず、テレビ関連の依頼は大体引き受けてくれます。
チャンネル設定に何度も失敗する場合には、テレビの修理も合わせてお願いできる場合もあります。
アンテナ工事の基本料金にチャンネル設定が含まれていることもあり、アンテナ設置やテレビ修理のついでにお願いできます。
電波が弱いなどの原因の場合には、素人での対処は困難です。
お電話口で相談することで、原因を特定してもらえることもあります。
・電波が弱いというメッセージがでる
・良く分からないエラーがでる
・何度チャレンジしても映らない
上記であればアンテナやテレビの不具合が考えられますので、問い合わせてみると良いでしょう。
テレビ準備方法〈引っ越し先別〉
集合住宅の場合

アパートやマンションなどの集合住宅は、建物全体で地デジ受信する共有のアンテナが設置されていることがほとんどです。
共有のアンテナが設置させている場合には、テレビ本体のコンセントを繋ぎ電源を入れれば視聴できます。
古い中古マンションに引っ越しされる場合、共有アンテナが設置されていないこともあります。
個人で手配する際にはご自身で専門業者にアンテナ設置を依頼するか、ひかりtv やケーブルテレビにするか検討する必要があります。
アンテナの設置にはアンテナの購入代金・工事費用3~8万円ほどの初期費用がかかります。
光テレビやケーブルテレビに加入する際にもアンテナと同じくらいの初期費用がかるようです。
転居先のアンテナ事情は前もって確認しておきましょう。
一戸建ての場合

新築の一戸建ての場合には、テレビを受信するシステムは備わっていません。
したがって、アンテナ設置工事依頼するか、ひかりTVやケーブルテレビなどの契約をする必要があります。
何らかの契約をしない限りテレビ視聴はできませんので、前もって準備するようにしましょう。
ー関連記事ー
☞【新築戸建てでテレビを視聴する方法!アンテナ設置のための知識とは?】
賃貸の場合

賃貸物件の場合、マイホームと異なり「原状回復義務」があることに留意します。
退去時には入居時の部屋の状態へ戻さなければなりません。
例えアンテナを新設したり最新の地デジアンテナへ交換したりアップグレードするような工事であっても同様です。
大家さんやオーナーさんの許可がなければ賃借人の支払いにより元へ戻すことになります。
さらに工事で壁に穴を開けたり住居に傷がついたりした場合は賠償問題に発展しかねません。
必ず前もって大家さん等へ確認しましょう。
またアンテナの設置自体を禁止している地域もあるので、アンテナを設置することになった際には注意が必要です。
その他賃貸物件で準備すべきことは上記「集合住宅の場合」か「一戸建ての場合」も参考になります。
賃貸物件で集合住宅の場合には、テレビのコンセントやケーブルを挿して、チャンネル設定を行うとテレビを見られることが多いです。
引っ越しでテレビを梱包する前に準備すること

引っ越し業者のオプションを確認する
引っ越し業者のオプションに「らくらくパック」などが盛り込まれている場合、テレビの梱包も全て業者が担ってくれます。
そのようなオプションがない、予算によりつけられない場合にはご自分で梱包する必要があります。
ご自身で梱包する場合にも、大手引っ越し業者ではテレビ専用の梱包ケースを用意してくれることもあります。
引っ越し業者に一度確認してみると良いでしょう。
梱包時に必要な道具を準備する
ご自分で梱包する際に購入時のダンボールがあるとスムーズですが、購入後に処分してしまう方も多いです。
その場合には、衝撃緩衝材(プチプチ)や布団や毛布などを用意しテレビを包み込みます。
衝撃緩衝材は、ホームセンターなどで大き目のものを購入しておくと便利です。
その他に荷造り札、汎用シール、サインペン、結束バンドなども準備しておきましょう。
こちらはテレビの配線を管理するときにあると便利です。
テレビの受信手続きを行う
・NHKの住所変更
引っ越しする時には、NHKの住所変更手続きも忘れないようにしましょう。
NHK受信料の窓口はこちら↓
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/AddressChangeMenu.do
・ひかりTVの手続き
フレッツ光などに加入されている方は、変更や解除などの手続きが必要です。
解約には手数料が生じる場合もあります。
・ケーブルテレビの手続き
引っ越し前のお宅でケーブルテレビに加入し継続利用されたい方は、変更手続きが必要です。
旧居での設備撤去や転居先での施工工事が必要になる場合もありますので、1カ月前を目安に前もって手続きするようにしましょう。
引っ越しでテレビを梱包する手順

こちらでは、テレビの梱包手順についてご紹介します。
テレビは精密機械で重量もあるので、自力で梱包する際にはなるべく2人以上で作業するようにしましょう。
手順①テレビ本体、周辺機器の電源を切る
まずはテレビ本体や録画機器などの電源を切ります。
いきなりコンセントを抜くのではなく、電源スイッチで電源を切り確実に電源が切れているか確認をしてから抜きましょう。
リモコンの電池は他の荷物によってボタンが押されっぱなしになる可能性もあります。
電池の消耗に繋るので抜いておきましょう。
各梱包物には「テレビのB-CASカード 」「リモコン」などメモをしておくと便利です。
手順②B-CASカードや説明書を確認する
最近のテレビの多くには「B-CAS(ビーキャス)カード」が差し込まれています。
このカードは必ずしも抜く必要はありません。
しかし、引っ越しの振動などによる接触不良を心配される方は抜いておきましょう。
B-CASカードは厚紙を入れた封筒などに入れ、本体と一緒に梱包します。
この時、取扱説明書もひとまとめにしておくと便利です。
手順③配線に目印をつける
転居先でスムーズに配線を接続するために、配線を外す前に機器のうしろの配線周りを写真に撮っておきましょう。
そしてどの配線がどの差込口に接続するか、それぞれに目印をつけます。
この時、付箋やマスキングテープがあると便利です。
用意した付箋やマスキングテープに、抜いたケーブルと端子部に同じ番号を記載し貼っておきます。
どの配線がどの端子に接続するか分かりやすく接続作業がスムーズになります。
手順④テレビ本体を梱包する
・購入時の箱に梱包
購入時のダンボールが保管されている場合には、そちらの箱に入れることがベストです。
箱に入れる際にはテレビ本体・コードは定位置に収め、余計なものは入れないようにしましょう。
・購入時の箱が無く自力で梱包
専用の箱が無い場合には衝撃緩衝材や布団・毛布などで本体をすっぽりと包みます。
液晶画面と同じサイズにカットしたプラスチック段ボールを、画面側に貼り付けておきます。
段ボールでテレビの前面と後面を覆い布テープで固定、テレビ上部にも段ボールを被せましょう。
テレビを梱包する際の注意点
注意点①梱包はテレビを立てた状態で行う
横に寝かせた状態でテレビを運ぶと、運搬の振動で故障する危険性があります。
その為、運搬時立てた状態で荷積めすることを想定した上で梱包しましょう。
特に購入時の箱がなく自力で梱包される時には、きちんと自立するか確認しながら慎重に進めることが大切です。
注意点②液晶画面は丁寧に保護する
テレビの液晶画面は強い圧力がかかると破損しやすく、とてもデリケートです。
本体とコンセントなどを一緒に包んでしまい、液晶画面を傷つけてしまうという失敗が多くなっています。
その為、液晶画面はプラスチック段ボールを画面に貼り付け、別途保護しておくと安心です。
注意点③注意書きを箱に記載する
梱包した箱には運搬時に引っ越し業者が気づきやすいように、以下のように記載しましょう。
その際、白い紙に記入し箱に貼り付けたほうが、引っ越し業者は把握しやすいです。
・この面を上に
先述でも申し上げた通り、寝かせた状態でテレビを運ぶと運搬時の振動で故障する場合があります。
箱の向きを正しく伝えるために記載します。
・壊れ物注意
運搬に注意が必要であることを伝えるために記載します。
・液晶パネル側 取扱注意
液晶画面側は特に注意が必要です。
破損を防ぐために記載しましょう。
引っ越しの際にテレビを処分する方法

テレビを処分する場合、家電リサイクル法に基づき適切に処分する必要があります。
まずはテレビの購入店舗や家電リサイクル店に連絡をしてみましょう。
リサイクル料金や収集送料を支払えば処分してもらえます。
直前に確認すると収集日が希望日と合わないこともあるでしょう。
その際には不用品回収業者などにもお願いができますが、割高になることもあります。
自治体のサイトなどで早めに確認することをおすすめします。
引っ越しの際にアンテナを処分する方法

古いアンテナの撤去は、設置場所にもよりますが基本的には専門業者に依頼しましょう。
アンテナの多くは外壁や屋根上など、撤去作業には危険が伴います。
年期の入ったアンテナは長年の雨風の影響で錆びついており、破損し落下する事も考えられます。
旧居を傷つけるだけでなく、最悪の場合人を巻き込んだ事故が生じることもあります。
専門業者に連絡をし、簡単なヒアリングと日程調整を行うだけで専門スタッフが対応してくれます。
撤去依頼をするとご要望に応じて、処分まで対応してくれる業者がほとんどです。
ー撤去作業を含む関連記事ー
テレビで動画配信サービスを見る方法

動画配信サービスとは、インターネット回線を使いドラマや映画、アニメなどの動画を視聴できるサービスを指します。
最近では「ビデオ・オン・デマンド(VOD)」や「定額制動画配信サービス(SVOD)」などとも呼ばれています。
スマートフォンの普及に合わせて利用者がどんどん増加しています。
国内で有名な動画配信サービスと言えば、「Hulu(フールー)」や「Netflix(ネットフリックス)」「Amazonプライムビデオ」「dTV」「U-NEXT」などがあります。
それでは、これらのサービスをテレビで見る方法について詳しくご紹介していきます。
動画配信サービスを見るための設定手順
まず、テレビで動画配信サービスを見る方法についてご紹介します。
・スマートテレビで視聴する
・メディアストリーミング端末で視聴する
・STBやブルーレイなどの周辺機器で視聴する
・PS4®などのゲーム機で視聴する
それでは、動画配信サービスを見るための設定手順についてご紹介します。
尚、動画配信サービスのアプリのダウンロードですが、テレビや使用端末にすでにダウンロードされているサービスもあります。
その場合にはダウンロードは不要です。
また、スマートテレビで視聴する場合には、アプリボタンを押すだけで動画視聴が行えます。
映らない場合は?
上記設定手順を行い、テレビに動画が映らない場合は以下方法を試してみて下さい。
動画配信サービスはインターネット回線を使っているため、テレビの不調を直す方法とは異なります。
①インターネット環境に不具合がないか確認する
②同時に視聴している人がいる場合、その使用人数を減らす
別の端末から動画配信サービスに同時にログインすると視聴できなくなることがあります。使用していない端末はこまめにログアウトしましょう。
③アプリの再起動・再ログインを行う
④メディアストリーミング端末やスマートテレビの再起動を行う
テレビや周辺機器に問題がある場合もあります。
使用端末に問題がなく、いくらやっても改善しない場合には「動画配信サービスのサポートセンター」に問い合わせて相談してみましょう。
アンテナ修理業者の選び方

テレビが映らない原因がアンテナの不具合であった際には、ご自分での対応は避けプロにお願いするようにしましょう。
最近ではアンテナ修理も様々な業者が請け負っていますが、こちらではアンテナ修理業者の選び方のポイントを大きく3つご紹介します。
アンテナ修理は、便利屋や街の電気屋、ホームセンターなどでも受けてくれます。
しかし、アンテナ修理を請け負うからといって必ずしも専門的な知識が豊富とは限りません。
専門業者以外では、実際に工事を担うのは下請け業者であり、アンテナ専門ではないスタッフも在籍しているため技術が未熟な場合もしばしばあります。
工事実績を重視して選ぶことも大切です。
長年の実績は、安価な工事費や工事スタッフの質の高さ、サービスの充実さの表れです。
ホームページで発信している工事の様子や、利用者の口コミ・評判、保証サービスの実績なども参考にしながら、信頼できる業者であるかしっかりと見極めましょう。
みずほアンテナでは年間3万件以上のアンテナ新規設置や修理工事を行っており、在籍する工事員の技術や経験も豊富です。
・
最近では、アフターサービスが充実した業者が増えています。
保証期間を設けている業者も多く、保証内容や保証期間なども業者ごとに異なります。
また、アンテナの故障や不具合は予測することはできません。
いつか突然トラブルは巡ってきますので、365日即日で対応している業者を選ぶ事も大切です。
一部悪徳な業者は保証について説明しながらも保証書を渡さず、結局保証による施工を請けないケースもあるので注意が必要です。
アンテナ工事のことならみずほアンテナ

テレビ視聴に不具合が生じたら、まずは焦らずに発生している症状を順番に確認しましょう。
テレビ画面にノイズが走っているのか、E201やE202などの表示が出ているか、全く映らないのか、特定のチャンネルだけ映らないかなどテレビ画面の症状を確認しましょう。
不具合が発生する時間帯や天候を確認することも大切です。
細かい内容を確認することで、原因が特定できる場合があります。
テレビ視聴の不具合で一番多い原因は配線のトラブルであり、お客様の手ですぐに治すことができます。
次に多い原因はテレビのチャンネル設定で、初期設定の”チャンネルスキャン”をする必要があります。
お持ちのテレビの説明書などを確認し、チャンネルスキャンを行ってみましょう。
もし上記の方法を行ってもテレビが映らないという場合は、アンテナに不具合が発生している可能性が高いです。
アンテナの不具合には、屋外配線の劣化やブースターのショート、アンテナの方向のズレなどがあります。
その場合、お客様の手で解決することは難しい状況になっています。
症状を確認し、お客様の手で治せる場合は時間もコストもかかりません。
しかしアンテナ周辺に不具合が生じている場合は、高所作業になりますのでご自身での修理はお勧めいたしません。
その場合には、アンテナ業者に問い合わせみましょう。
みずほアンテナは365日即日対応を受け付けております。
不具合が生じた場合はお電話口でヒアリングを行い、経験豊富な自社の工事担当スタッフがご自宅にお伺いします。
アンテナ工事はアフターサービスもしっかりしている、みずほアンテナへお気軽にお問合せ下さい。
まとめ|引越し後にテレビが映らない時は専門業者に相談しよう

引っ越し先でスムーズにテレビを視聴するためには、引っ越し前に入念に準備しておく必要がります。
端子やケーブルなどの印付けや、丁寧な梱包、映らない場合の原因や対処法を事前に把握しているかいないかで結果は大きく変わってきます。
慌ただしい引っ越し作業、一つでもトラブルを減らすためにも、前もってやりやすい方法を選択し準備しておくことが重要です。
万が一の場合に備え、専門業者を予め調べておくことも良いでしょう。
一通りの対処をほどこしてもテレビが映らない場合には、是非みずほアンテナにご相談下さい。
ー関連記事ー
☞【テレビが突然映らない!原因や自分でできる対処法を紹介】
☞【新築に引っ越したらテレビが映らない!?そんな時はすぐに視聴できるアンテナがおすすめ】